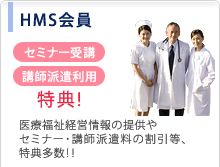
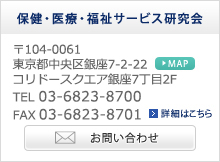
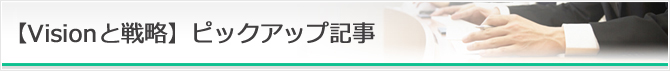
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
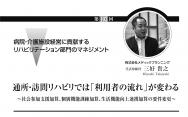
通所・訪問リハビリでは「利用者の流れ」が変わる
~社会参加支援加算、個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算の要件変更~
2021年度介護報酬改定の議論も大詰めを迎え、12月23日の介護給付費分科会にて、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告が提示された。今後、これに伴い改定項目が整理されていくところであるが、今回の介護報酬改定では、コロナ禍での介護報酬改定とあって、「1.感染症、災害への対応力強化」が明示されている。また、前回の介護報酬改定に引き続き「2.地域包括ケアシステムの推進」が明示され、認知症、看取りをはじめ、介護報酬全体に必要な項目が入っている。そして、今回の介護報酬改定で特徴的なのは「3.自立支援、重度化予防の取組の推進」である。
「リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化」では、これらをバラバラに対策していくのではなく、一体的に強化していくことで、重度化の予防を推進する意図が見える。ここ数回の介護報酬改定にて、口腔、栄養は強化されてきた項目ではあるが、それらを今度は、リハビリテーション・機能訓練と併せて対策を講じていく必要がある。また、介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進では、リハビリテーション実施計画書をデータ化している「VISIT」や主に栄養、服薬など幅広く利用者の状態をデータ化する「CHASE」を導入する。これは、利用者の自立支援や重度化予防を今までのような各事業所の判断だけではなく、全国的なデータベースも使用して、事業所と利用者がフィードバックを受けながらPDCAサイクルによってより効果的な介護やリハビリが受けられるようにケアプロセス全体を見直していこうという意図である。

2期連続でのプラス改定も
非常に厳しい大改定となる
令和3年度介護報酬改定は、改定率が+0.7%と2期連続でのプラス改定となった。うち0.05%はコロナ禍対策として令和3年9月までの限定措置であるため、実質0.65%のプラス改定となる。しかし、近年の介護職の人件費の高騰を勘案するとそれに見合った改定とは言えず、介護事業者は厳しい事業運営を強いられる。また、今回のプラス改定については、健保組合や経団連などから国民負担増について厳しい意見も出ており、いずれも介護事業者側の自助努力、革新を求めるものである。プラス改定は、40才以上が支払う介護保険料の更なる上昇をもたらし、家計や企業の負担が増える。また、利用者の自己負担による支払額も増えることになることも忘れてはならない。
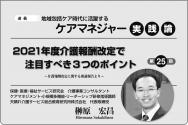
前号では、居宅介護支援の改定事項を中心に書かせて頂きましたが、今回は、昨年12月23日に既に「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」が出ていることもあり、もう少し広い視野で、改定の全体像を捉え直してみたいと思います。
本稿が皆様のお手元に届くころには、新報酬の答申が行われる時期になるかもしれませんが、ここで述べる全体像には変わりはないものと思います。私が捉えた今回改定で注目すべき点は以下の3点です。
⑴より基本的な内容の充実
⑵実態に即した内容も多く含まれる
⑶自立支援・重度化防止の推進
以上3点について、一つずつ見ていきますが、当然ながらまだ確定の内容ではありませんのでご承知おき頂きたいのと、表現を簡潔にするために、文言を省略している箇所がありますので、正確には分科会の資料をご覧頂きたいと思います。
■より基本的な内容の充実
今回の改定内容や議論の経緯を見て、まずはじめに思ったのが、より基本的な内容の見直しが多い、ということでした。以下、主要なところを11項目にまとめました。
①感染症対策の強化(指針・委員会・研修・訓練)※3年の経過措置
②業務継続の取組(計画・研修・訓練)※3年の経過措置
③虐待防止の推進(指針・委員会・研修・担当者)※3年の経過措置
④施設系サービスにおいて安全対策担当者を定める※6月の経過措置
⑤介護職員の認知症介護基礎研修受講※3年の経過措置
⑥看取りについてACPのガイドラインに沿った取り組み
⑦口腔、栄養改善の取組を基本サービスとして位置づける
⑧通所系の入浴介助加算について入浴計画に基づく介助を評価
⑨ADL維持等加算を通所介護に加えて、認知症デイ、介護付きホーム、特養に拡充
⑩尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、日々の過ごし方等について計画(CHASEデータ提出とフィードバック)
⑪褥瘡マネジメント、排せつ支援加算についてアウトカムを評価
①~④については、感染症対策、業務継続、虐待防止、安全対策ということで、経過措置付きの内容となっていますが、いずれも「マネジメント」が問われる内容になっていることが注目すべきポイントだと思います。より基本的な介護の質を保つためにも、こうしたマネジメントが重要である、ということです。
⑤の認知症介護基礎研修受講についても、介護の質を保ち、向上させるために必要と考えてのことでしょう。⑥と⑦については、より基本的なことが他サービスに横展開されたり、基本報酬化されていく、という方向性です。
そして、⑧~⑪については、この後にも述べる、自立支援やアウトカム(成果)を評価する内容になっています。とりわけ⑩の「医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、日々の過ごし方等について計画」については、どんな内容になるか、気になるところです。「日々の過ごし方」についてどう考えるのかが注目ポイントになるものと思います。
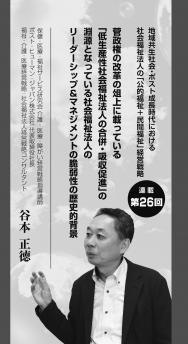
菅政権の改革の俎上に載っている
「低生産性社会福祉法人の合併・吸収促進」の
淵源となっている社会福祉法人の
リーダーシップ&マネジメントの脆弱性の歴史的背景
社会福祉法人の制度創設期は、昭和20年代、我が国が終戦による海外からの引揚者、身体障害者、戦災孤児、失業者などの生活困難者の激増という困難に直面していた頃であった。戦後の荒廃の中、行政の資源は不十分で、当時の政府には民間資源の活用の道しかなかった。このため、社会福祉事業を担う責務と本来的な経営主体を行政(国や地方公共団体等の公的団体)としつつも、事業の実施を民間に委ね、かつ、事業の公益性を担保する方策として、行政機関(所轄庁等)がサービスの対象者と内容を決定し、それに従い事業を実施する仕組みである「措置制度」が設けられた。そして、措置を受託する法人に行政からの特別な規制と助成を可能とするため、「社会福祉法人」 という特別な法人格が活用されたわけである。税制優遇を受ける一方、社会的信用の確保のため、基本的に「社会福祉事業のみ」を経営すべきという原則論の下、所轄庁の指導監督を受けてきたという歴史的諸制約から、社会福祉法人は民間事業者ではあるものの、行政サービスの受託者として公的性格の強い法人となり、市場原理で活動する一般的な民間事業者とは、異なる原理原則の下、発展していくことになったのだが、それによる組織的マネジメントとリーダーシップの脆弱性を育ててしまうという弊害も同時に進行し、その影響を図らずも受けてしまった社会福祉法人組織が今も全国に存在している。
社会福祉法人特有の組織的マネジメントとリーダーシップの脆弱性を育ててしまったその要因は、例えば所轄官庁による法人本部を通らない「施設運営毎の指導監督」といった進め方の影響を受けてできたもの(施設任せ)、公的性格が強いことから厚生労働省、都道府県、市町村などの天下り先として非常勤理事長や当て職理事長、名誉職的な理事長人事の常態化の結果によるものなどがある。しかし、組織マネジメント&リーダーシップの脆弱化の誘水となった究極の要因と考えられるのは、施設ごとに現場任せのマネジメントを許してしまった法人の事例、またはそれとは真逆に理事長あるいは副理事長、専務理事、常務理事等業務執行理事に権限を集中させ、現場にものを考えさせない思考停止マネジメントを施してしまった法人の事例が代表的である。
令和の時代に入り、菅内閣となって発表された規制改革の目玉メニューの中に、そんな社会福祉法人をまな板の鯉としたような項目が入っている。「小規模・零細・低生産性社会福祉法人等の大規模化促進」である。リーダーシップとマネジメントの機能不全を起こしている社会福祉法人を狙い撃ちとする形といえる。ここで問題なのは、「低い生産性」の社会福祉法人は何も零細・小規模社会福祉法人に限らないと言う点である。政府・財務省・厚生労働省は「大規模化」により、社会福祉法人の生産性の低下を回避できると踏んでいるようだが、それは事実認識が甘いと考えられる。
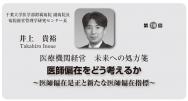
医師偏在をどう考えるか
~医師偏在是正と新たな医師偏在指標~
❶第9次医療法改正における
医師偏在是正と
新たな医師偏在指標
平成30年の第9次医療法改正では、医師偏在を是正する改正が行われた。その趣旨は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずるものである。
その具体的な内容としては、①医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設、②都道府県における医師確保対策の実施体制の強化、③医師養成過程を通じた医師確保対策の充実、④地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応等があげられている。第6次医療法改正での地域医療構想を推進するためにも、医師偏在対策は重要な政策課題である。
医師偏在を具体的に示す指標としてしばしば人口10万人当たりの医師数が用いられており、今日も一定の意義を有すると考えられる。しかしながら、医師偏在指標が提唱され、そこでは受療率、将来人口構成、医師の性別や年齢分布、患者の流出入等を調整した推計が行われている。
図表1の上段が人口10万人当たりの医師数であり、下段が新たな医師偏在指標となっており、計算方法の変更によりその順位変動もみてとれる。国は、この医師偏在指標を医師確保計画にあわせて見直すこととしている。
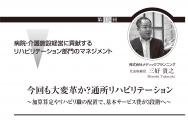
今回も大変革か?通所リハビリテーション
~加算算定やリハビリ職の配置で、基本サービス費が3段階へ~
2018年介護報酬改定でもっとも影響が大きかったのは通所リハビリだった。4時間以上のサービス提供時間の基本サービス費が1割近くも減算された。筆者のクライアント先でも元々利益率が1割無かった通所リハビリは、赤字に転落した。そこでの対策は、サービス提供時間を6時間から7時間に延長したり、単価の高い、リハビリマネジメント加算Ⅱ以上を算定したり、場合によっては、1日型のサービス提供時間をやめて、3時間の短時間型へ移行した通所リハビリも多かった。このように、4時間以上の基本サービス費の減算は「リハビリだけなら4時間で十分で、それ以上は、食事や入浴やレクリエーション中心の通所介護と同じ」という意図であったと考えられる。
よって、通所リハビリの収入のうち多くを占める基本サービス費への「テコ入れ」が行われたばかりで、さらに、今回はコロナ禍での改定であるため、筆者は、通所リハビリに関してはマイナーチェンジ程度だろうと思っていた。
基本サービス費本体の変更
しかし、11月16日に行われた介護給付費分科会では、通所リハビリの報酬体系を今までの「サービス提供時間(時間区分)+利用者人数(規模別)」から(図1)のように抜本的に変革する案が提示された。

コロナ禍での実地指導の現状
〜居宅介護支援と処遇改善加算が要注意に〜
介護報酬改定審議が終盤を迎える中で、実地指導が粛々と進められている。今年前半は新型コロナウイルスの影響で、当初予定されていた日程の大部分が中止か延期となった。その影響もあり、半日型の指導が急増しているのが今年の実地指導の傾向である。一件を半日で完了して、一日で二件の事業所を回る。この件については、昨年2019年5月29日の厚生労働省老健局から「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」が発出されたことから、今後は半日型で一日に二件回る事が主流となることが見えていたが、それをコロナ禍が後押しした形で、一気に半日型に移行している感が強い。
この通知は、実地指導を効率化して年間の指導件数を増やすことが主たる目的である。従来から厚生労働省は介護事業所を所轄する自治体に対して、少なくても指定有効期間である6年以内に一度は実地指導を行い、その事業所に問題ないことを確認してから指定の更新手続を進めるように通知を出している。しかし、介護事業者の急増によって物理的に困難な状況が続いているのが現実だ。6年を超えて何年も実地指導が行われていない介護事業所も普通に見かけるようになった。2019年通知では、実地指導の効率的な実施によって、従来は一日作業であった現地指導を半日に短縮して、一日に複数件の実地指導を行うように求めた。それによって、指定有効期間である6年以内に一度は実地指導を行うことを実現することを目的とする。昨年は通知直後と言う事もあって、2020年度から実施するという自治体が多かったのも事実だ。今年度は、自治体の職員が標準確認項目での効率指導に慣れると共に、確実に半日型の実地指導が増加している。ただし、一日型の実地指導が無くなったわけではない。事業規模の大きい事業所、前回の実地指導で問題があった事業所、トラブル、クレームの多い事業所などは従来通りに一日型の実地指導が行われる。
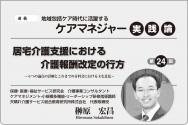
居宅介護支援における
介護報酬改定の行方
~6つの論点の詳細とこれまでの分科会における主な意見~
11月26日に開催された第194回介護給付費分科会では、居宅介護支援について取り上げられ、いよいよ大詰めとなる検討が行われました。本稿では、この時の資料に基づき、居宅介護支援における介護報酬改定の主な項目について、これまでの分科会の意見とともにまとめてみたいと思います。論点としては以下の6つが挙げられています。
■論点①
質の高いケアマネジメント
まず、特定事業所加算について、小規模事業所の中には、職員の配置要件などに関し、要件を満たすことができない事業所もある。そうした場合であっても、事業所間の連携を推進することにより、質の高いケアマネジメントを実現できると考えられる場合については一定の評価を行うため、事業所間連携を促進する加算区分を設定することも検討してはどうか、ということが提案されました。
さらに、特定事業所加算については、「多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」の加算要件への追加が提案されました。
また、現行の加算(Ⅳ)の算定要件については、加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)と評価軸が異なることや、医療と介護の連携を推進する観点から、加算の名称について、算定要件に沿った名称として、例えば、「医療介護連携体制強化加算(仮称)」と見直してはどうか、とされました。
最後に、居宅介護支援事業所の公正中立なケアマネジメントのための取組みの一環として、運営基準に「① 当該事業所のケアプラン総数に利用を位置付けた各サービスの利用割合(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)」「② 前6月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の提供回数のうち、同一事業者によって提供されたものの割合」について、利用者へ説明することを明示し、その内容を介護情報公表システムの運営情報に掲載することが提案されました。
(分科会での意見としては、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していない理由で一番多いのが利用者の中重度者割合要件を満たせないこととなっているが、他の要件とは異なり、事業所自体の努力でどうにかできるようなことではなく、利用者の選別にもなりかねないため、見直しを検討するべき、とありましたが、これは見送られそうです。)
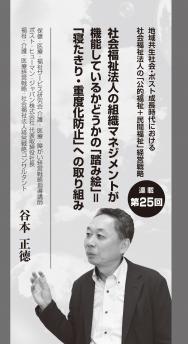
社会福祉法人の組織マネジメントが
機能しているかどうかの「踏み絵」=
「寝たきり・重度化防止」への取り組み
2021年介護報酬改定の議論が山場を迎えて、この紙面を読者の方が読まれる頃には最終結論は明らかになっていると思われる。横断的テーマの中核と考えるべき「自立支援・重度化防止」への取り組みの議論の動向で筆者として敢えて注目するのは、社保
審-介護給付日分科会第194回令和2年11月26日資料7の「自立支援重度化防止の推進〜3.重度化防止の推進等について」の最新の中身である。何度も以前から言及をしているが、2021年介護報酬改定の中身のクライマックスは、「自立支援・重度化防止の推進」だと断言できる。このテーマは直接「国民」に影響を与えるからである。先日、筆者が代表を務めるポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)に所属する自立支援介護メソッド導入教育シニアコンサルタントが、新たに契約した北海道内の医療法人の介護老人保健施設においてコンサルティング開始前にケアの現状把握のために視察・ヒヤリングを実施した。当該コンサルタントは、その老健の施設長に次のような感想を述べた。「現状については、入居者本位ではなく、職員本位の運営・ケアの内容ですね」と。いわゆるアウトカムを追求しない「お世話型介護・安静介護」は、職員の負担をいかにゼロにするかが最終目標となるため、その場合、入居者の権利擁護・尊厳の護持は、如何せん優先順位が低くなるのが現実である。しかし、これが介護保険制度・介護報酬改定の改革により、高齢者の尊厳護持と経営者の利害がシンクロし始めると、ようやく国民の利益につながる制度改正・報酬改定となるわけである。
全ての、この世の中にある「組織体」が有機的に、生産性を向上させ、社会にインパクトを与えるサービスを提供し続けるために必須事項は、有資格の配置ではない。組織において強いリーダーシップを効かせ、リーダーが設定したゴールに向かって、その達成のために強く、細かく、愛情たっぷりのマネジメントが機能する事こそが必須事項である。有資格という「個」を配置したからといって、その「個」が課題を解決できない。そこに優秀なリーダーシップが機能しなければ、何も生み出すことはできないというのが、組織論の原理原則である。この点を、社会福祉法人、介護老人保健施設経営の医療法人の経営者は肝に命じる必要がある。特に社会福祉法人は、組織論の科学的な原理原則から外れたリーダーシップとマネジメントを施しているケースが異常に多い。歴史が作り上げた習慣・カルチャーとも言える。現場の理解と納得が究極の目的としているというミスリード、ミスマネジメントが横行している。「うちの法人はゆる〜くマネジメントしているんですよ〜」と能天気にのたまう施設長に最近遭遇したのであるが、「ゆるーいマネジメント」でたらたら仕事をしていると、振り返ると20〜30才代は姿を消していくことを覚悟しておいたほうが良い。何故なら、「ゆるーいマネジメント」では「部下の成長が無い」からである。自分自身の成長が見込めないような組織に、未来のある20〜30才代は、勤め続ける理由がない。いつの時代も、「若い世代・青年層」が生き生きと成長できない組織は必ず衰退する運命にある。過去の習慣を新たな習慣作りにより「上書き」をする必要がある。
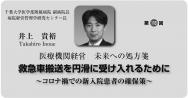
救急車搬送を円滑に受け入れるために
~コロナ禍での新入院患者の確保策~
➊新入院患者獲得の重要性
新型コロナウイルスで患者数が減少した医療機関がほとんどであり、コロナ禍で今年度の業績は極めて厳しくなる病院が多いことだろう。病床稼働率が元に戻らない病院では、稼働率を優先して治療終了後も入院を延ばすケースが多いようだ。特に重症度、医療・看護必要度の経過措置期間が9月末から年度末まで延長になったため、とりあえず稼働額を繕うために退院させない病院が増えている。ただ、在院日数を延ばせば稼働率は上がるが、患者1人1日当たりの収入である入院診療単価は下落する。もちろん財務の観点からみれば、入院稼働額は患者数×入院診療単価であるから、病床を開けておくよりも単価が下落したとしても患者がいた方がプラスになるのも短期的に考えれば事実だろう。ただ、入院診療単価は急性期のバロメーターであることは間違いがない。入院診療単価が下落することは急性期らしさから遠ざかることを意味し、稼働率を優先するのであれば地域包括ケア病棟に転換した方が有利になる可能性も大である。高単価が儲かるわけではないが、現状の地域医療構想でも低単価で急性期を主張することは難しいだろう。さらに、DPC/PDPSに参加していれば効率性係数が下落するし、意図的な在院日数延長はスタッフのモチベーションにも影響するだろう。院長の「在院日数を1日延ばせ!」という号令には皆がある程度無視をすることが多いが、愚直に実行する組織ではそれに慣らされてしまっているのかもしれない。このことの一番の懸念材料は、SNSなどで情報が拡散することだ。「あの病院に行ったら必要以上に入院させられる。」と、地域で噂が飛び交ってしまうかもしれない。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
