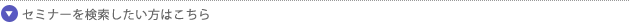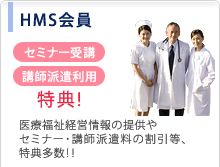
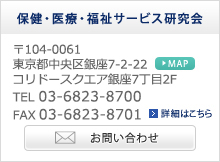
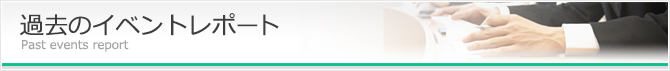
現在64件の情報があります。

カマチグループが新規開院した回復期リハビリテーション病院などの事業概況説明会「医療連携会」が8月22日、都内のホテルで開かれた。
写真入り記事はこちらからダウンロード

「21世紀型のコミュニティ再生と2025年に向けたあるべき医療・介護・福祉経営」
~地方創生や一億総活躍社会の実現に貢献する地域包括ケアシステム構築とま”まちづくり”の取り組み~
地域包括ケア時代の事業経営に不可欠なのは“まちづくり”の視点
まち全体の将来を視野に事業経営を考える
地域包括ケアシステムの実現に向けた動きが本格化する中で、医療・介護・福祉サービスの提供体制はどうなっていくのか。我々事業者に問われていることを一言でいうならば、自分たちのまちをどうしていくのか、また、その中で自分たちがどのような役割を果たしていくのか、自ら考え行動していく“主体性”に尽きるのかもしれない。
これまではどちらかというと、急増する高齢者への対応がクローズアップされてきた。これに対して今、活発化しているのは、少子高齢化および人口減少にどう対応していくのか、という議論である。生産年齢人口が減少すれば当然、税収は減り、社会保障費は抑制せざるを得なくなる。同時に医療・介護サービスの担い手の確保も困難を極めることは間違いない。つまり地域包括ケアシステムが掲げる「住み慣れたまちで最期まで」を実現するためには、人口減少、少子高齢化に正面から向き合わざるを得ないのであり、まち全体の人口動態なども視野に入れた事業経営が、求められてくるのである。
一方で、我が国の少子高齢化の実情は、地域によって相当な違いがある。大都市圏のようにこれから一気に高齢者が増える地域もあれば、すでに高齢者人口が頭打ちになっている地域もある。自治体への権限移譲が進められているが、これは均質的なサービスを全国に行き渡らせるやり方では対応できなくなっているからであり、各地域の実情に合った仕組みをそれぞれの自治体が主体的に構築していくことが、早急に求められている。
事業者にとって大切なのは、この流れの中で、自らの立ち位置をいかに獲得していくか。自らが事業を運営している地域の“まちづくり”の担い手になることを、本気で考えていく時代に突入したといえる。
「生涯活躍のまち」構想と地域包括ケアシステム
本特集で紹介するセミナーは、まさに“まちづくり”あるいは“コミュニティ再生”といったことをキーワードに地域包括ケアシステムを捉え、その中で医療・介護・福祉経営はどうあるべきかをテーマにしたものである。
政府は一昨年から「地方創生」を掲げ、その一翼を担う施策の一つとして「生涯活躍のまち(日本版CCRC)」構想を打ち出している。この構想が、地域包括ケアシステムが目指すものと大きく重なり合っていることに着目したい。
『「生涯活躍のまち」構想(最終報告)』によれば、生涯活躍のまち構想とは、「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や“まちなか”に移り住み、地域住民や多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような地域づくりを目指すもの」と記されている。また、その意義については、①高齢者の希望の実現、②地方へのひとの流れの推進、③東京圏の高齢化問題への対応、という3つの点が挙げられている。
この構想と従来の高齢者施設との大きな違いは、要介護状態になってからではなく、健康な段階からの入居が想定されていること。高齢者は、社会活動に積極的に参加する「主体的な存在」として位置付けられ、地域社会の中で多世代と交流できるようなオープン型の居住が基本となっている。単に高齢者のための福祉施設を整備するという発想を越えた、“まちづくり”そのものであり、中でも「医療・介護が必要になった時には地域で安心して継続的なケアが受けられることを目指す」という点で、地域包括ケアの目指す方向性と一致している。
セミナーでは、このようなまちづくりの先進的な事例を紹介している。最前線を行く講師陣のレクチャーに加え、シンポジウムにおける活発なディスカッションの模様も掲載した。我が町、我が事業所のこれからを考える一助して頂きたい。
“まちづくり”にまで踏み込んだ
根本的な対策が地域包括ケアのカギに
地域包括ケア研究会座長
介護給付費分科会会長
慶応義塾大学 名誉教授
田中 滋 氏
2025年に向けて構築が急がれている地域包括ケアシステム。「それは単なる高齢者政策ではなく、まちづくりそのもの」と話すのは、地域包括ケア研究会座長の田中滋氏だ。その実現に向けて今、地域に何が求められているのか、田中氏は地域包括ケアシステムのコンセプトを解説した。
わが町に起きる危機を
クールに想定できているか
田中氏がまず示したのは、わが国が今、どのような事態に直面しているか、ということ。1950年から2015年までの65年間の高齢者人口の推移をみていくと、65歳以上人口は約8倍、75歳以上人口は約15倍、80歳以上人口に至っては約28倍に増えており、しかも近年は伸び方が加速している。要介護者の数も、介護保険制度が発足した2000年当時は200万人だったものが、今では500万人に倍増。この状況にどう対応していくのか、日本は今、必死に模索している。
しかしながら、「本当に危機はこの先にある」と田中氏。2022~24年の3年間で後期高齢者の数は一気に800万人も増え、2025年には2179万人に到達。一方で、2022年からは被保険者数の減少が始まり、2034年にはついに1号保険者の数が2号保険者の数を上回る見込みだ。加えて、地方の保険財政は現状、その地域だけで賄うことができず、大都市部で集められた保険料を地方に分配することで成り立っている。「制度設計上、これはたいへん怖い状況」と氏は危機感をあらわにする。
重要なのは、このとてつもない危機が決して他人事ではなく、全ての日本人が今、暮らしている“わが町”に起きる話だということ。田中氏は、「この怖さを感じながら自分たちの地域の将来像をクールに想定できているかどうか。小手先の対応ではとても追いつかず、“まちづくり”にまで踏み込んだ根本的な対策が、どうしても必要になる。そこで問われるのが地域包括ケアだ」と説明した。
病院勤務の看護師もリハも
全ては地域のために
重要なのは、在宅か施設か、という対比概念からの脱却だ。地域包括ケアシステムのキーコンセプトは、「おおむね在宅、ときどき施設(入院)、いつでも交流」、すなわち施設と在宅の循環的利用により、在宅を無理なく継続できるようにしていく、というものである。医療機関や介護事業所はあくまで在宅生活の支えであり、その機能も、そこにいる人員も全てが“地域のため”にある。例えば今、不足している訪問看護も、病棟の看護師が業務の一貫として訪問看護に出る、という方向に切り替えていけば、対応力は大きく広がるだろう。
また、地域包括ケアシステムは生活圏域の実情に合わせて構築していく必要があるが、そのカギとなるのが地域マネジメントだ。これからの自治体には、システムの企画力、そして地域の資源をネットワーキングするマネジメント能力が強く求められると、氏は強調する。
そして何よりも今、地域包括ケアシステムの構築が急がれる本当の理由は、2025年の先にあると田中氏。団塊ジュニア世代が後期高齢者になる2045年までにどうしてもやらなければならないのは少子化からの脱却であり、その対策を行っていくときに果たして地域包括ケアシステムがうまく機能するかどうかが問われるからだ。「つまり地域包括ケアシステムは、今いる高齢者のためだけではなく、次なる局面を乗り越えるために必須のシステムなのであり、だからこそ2025年までに必ず仕上げておかなければならない」と、氏は改めて示唆した。
元気な高齢者の移住で雇用を創出 多世代が共生する「日本版CCRC」
地方創生の鍵として注目を集める日本版CCRC構想。その本質を理解するために重要なのは、「介護で儲けるのではなく、介護にさせないことで儲ける」という逆転の発想だ。本セミナーでは、CCRC研究の第一人者、三菱総合研究所の松田智生氏が登壇し、その意義と可能性について語った。
三菱総合研究所 プラチナ社会研究センター
主席研究員チーフプロデューサー
松田 智生氏
予防医療の産業化により
税収を上げ、医療費を抑制
日本の高齢化率は26%と世界でも群を抜いて高く、1950年には60歳だった平均寿命は、今や80歳を超えている。この急速な高齢化に伴い一気に膨らんだのが医療費と介護費で、その額は今や50兆円と、国の税収55兆円の9割を超えている状況だ。これは日本にとって大変なピンチだが、「見方を変えるとそこに大きなチャンスがある」と氏は言う。日本ほど元気な高齢者に溢れた国はなく、日本版CCRC構想とは、“アクティブ・シニア”に着目したまちづくり構想である。
そもそもCCRC(Continuing Care Retirement Community)とは、健康時から介護時まで継続的なケアを提供するという、米国で広まった高齢者施設のコンセプト。日本では、米国とは異なる社会特性に合わせた日本版CCRCが、「生涯活躍のまち」として国の施策に組み込まれ、全国で進められようとしている。その特徴は、米国のCCRCが施設を中心としたものであるのに対し、日本版はまち全体を視野に入れている、ということ。高齢者に元気なうちに住替え、予防医療や健康支援を産業化して税収を上げる。一方では、介護予防による医療費・介護費の抑制を図る、というものだ。
しかしながらこの日本版CCRC構想は、誤解や先入観も多く正しく理解することが大切だと松田氏は強調する。まず地方移住ありきでなく、都市・郊外と多様な立地が対象だ。アクティブ・シニアを呼び込むことは、地域の高齢化が進むと思われがちだが、雇用が生まれれば若年層の転出を抑制し、働き世代の流入につながる。結果的に高齢化と人口減少を止めるのだ。そして介護で儲けるのではなく、介護にさせないことで儲ける、という逆転の発想だ。介護保険に依存した収益モデルは、国の限られた税収を考えれば厳しい。そこで予防や健康支援を中心としたモデルへの転換が、事業者の経営を安定させる。日本版CCRCとは、多世代が共生する “まちまるごとCCRC”であり、国が目指す地域包括ケアシステムそのものであり、市民・自治体・産業の三方一両得のモデルである。
ユーザー視点で魅力的な
住み替えのモデルを
地方再生法の改正で「生涯活躍のまち形成事業」が導入され、財政面でも地方創生交付金が設けられるなど、国は日本版CCRCを進める自治体を積極的に後押ししている。しかしながら、「それだけでは十分ではない」と松田氏。現状では介護度が改善された場合、介護保険ベースでの事業者の収益は下がってしまう。逆転の発想でもし介護度が改善された場合には、事業者に奨励金支給や減税制度を設けるなど、「介護インセンティブ」から「健康インセンティブ」に転換する制度設計が必要だと、氏は指摘する。
現在、全国の自治体の1割を超える約260の自治体が、日本版CCRCの推進意向を示している。これからはアクティブ・シニアの誘致合戦になるが、温泉とゴルフ場と病院はどこでもある。数あるライバルのなかでなぜわが町が選ばれるかが重要になる。「それは事業者視点でなくユーザー視点のストーリー性だ。シニアが年賀状に書いて自慢したくなるようなCCRCができるかが成功のポイントだ」と、氏は呼びかけた。
“ごちゃまぜ”が活力を生む! Share金沢の魅力と新たな事業展開
日本版CCRCの政府認定モデルとして注目されている「Share金沢」。高齢者、障害者、学生と、全ての住民が主体的にまちづくりに取り組む「生涯活躍のまち」はどのようにして創られたのか。社会福祉法人佛子園の雄谷良成氏が登壇し、地域コミュニティを創造する独自の取り組みを紹介した。
社会福祉法人佛子園 理事長
全国生涯活躍のまち推進協議会 会長
雄谷 良成氏
住民の声を受け、廃寺を復興
人々の交流の拠点に
1960年の創業以来、石川県白山市を拠点に福祉事業を展開してきた社会福祉法人佛子園。現在は約70もの事業を行っており、さまざまな地域コミュニティのモデルを創り出してきた。その一つが、Share金沢だ。
社会福祉法人がなぜ“まちづくり”なのか。それはグループホーム開設への近隣からの反対運動がきっかけとなっている。「このまちで半世紀も事業を行っていながら、地元の理解が得られない。自分たちは何をしてきたのかを改めて振り返ると、施設のことばかり考え、地域に対しては何もしてこなかったことに気が付いた」と雄谷氏。その反省から、佛子園はまちおこし事業を開始。そして2008年に立ち上げたのが、後のShare金沢の原型となった「三草二木 西圓寺」である。
西圓寺は、廃寺の復興を望む住民の声を受け、地域コミュニティセンターとして蘇らせたもの。まずは福祉の拠点として、高齢者の通所介護、および障害者の生活介護と就労支援を実施。さらに温泉やカフェを併設し、気軽に集える“憩いの場”として住民に開放した。
最大の収穫は、“ごちゃまぜ”の効果だ。象徴的なのは、認知症の女性が重度心身障害の子どもに、進んで食事介助を始めたこと。両者のふれあいにより、子どもは食事が食べられるようになり、認知症の女性も徘徊がなくなるなど、状態が安定していった。多様な人が一緒にいることで生まれる力の大きさを目の当たりにした雄谷氏は、「これまでの縦割りの福祉が、いろいろな可能性を阻害していたのではないか」と強く感じたという。
さらには住民たちも「寺を自分たちの手で守ろう」と、温泉の掃除などボランティアに参加。こうして人々の交流が活発になり、それがまちの魅力となって移住者も増え、世帯数は55世帯から71世帯に増加したという。
日本版CCRCの鍵は
交流人口をいかに増やすか
この西圓寺は、施設を拠点にした、いわば「施設型CCRC」。一方で、2014年開設のShare金沢は、これを地区レベルに拡大させた、「エリア型CCRC」である。
高齢者、障害者、学生の居住施設を設け、その周辺には天然温泉やライブハウスなどの商業区画を設置。周辺住民も気軽に利用できるようにした。高齢者の半数は県外からの移住者で、まちづくりの担い手として活躍。学生は月30時間のボランティアが入居条件となっており、家賃は相場の半額。「お金を介在させないことで、お互いの関係性が深まり、そこから“街に貢献していこう”という大きなエネルギーが生まれる。ごちゃまぜのコミュニティが生み出す活力が、まち全体を元気にしている。」
このShare金沢のさらなる発展形として、新たなCCRC構想「B’sプロジェクト」が2015年より動き出している。これは市町村レベルで行う「タウン型CCRC」で、住民自治の拠点として、これから本格稼働していく計画だ。
以上の経験から得たまちづくりのポイントは、交流人口をいかに増やすか、ということ。氏は「従来の病院や施設には、元気な人を集める仕組みがなかった。これからは地域に開かれた施設運営を行い、多世代交流の場をいかに創り出していくかがカギになる」と改めて強調した。
“まちづくり”は現場の実践から
事業所の創意工夫が地域を動かす
シンポジウム「21世紀型のコミュニティ再生と、2025年に向けたあるべき医療・介護・福祉経営」では、地域包括ケアの実現に向けて独自の取り組みを行ってきた4名のシンポジストが登壇。先進モデルである和光市をはじめ、さまざまな先駆的事例が紹介され、田中滋氏を座長に活発なディスカッションが展開された。
【座長】地域包括ケア研究会座長
介護給付費分科会会長
慶応義塾大学名誉教授
田中 滋氏
【シンポジスト】
和光市 保健福祉部長 東内 京一氏
公益社団法人日本医師会 常任理事・医療法人博仁会 理事長 鈴木 邦彦氏
つしま医療法人グループ 代表
一億総活躍国民会議 民間議員 対馬 徳昭氏
社会福祉法人佛子園 理事長 全国生涯活躍のまち推進協議会 会長 雄谷 良成氏
高齢者へのニーズ調査で
課題を詳細に把握
地域包括ケアシステムのモデル都市として注目を集める和光市。同市保健福祉部長の東内京一氏は、和光市が築き上げてきた独自のシステムと今後の展開について語った。
和光市は、これから日本一の高齢化の進展が見込まれる地域である。高齢化率は17.4%と低いが、これは若年人口の流入の影響によるもので、高齢者人口は相当な伸びを示している。中でも団塊世代が人口のピークを形成しており、今後、高齢者数のさらなる急増は必至だ。このような状況にあって、「今、介護予防をやらなかったらこの先どうなってしまうのか」という強い危機感が、和光市の取り組みの原点となっている。
次に示したのは、全国の要介護度別の認定者数だ。平成25年度では、要支援1~要介護1の軽度者が、要介護認定全体の46.7%を占めている。氏が問題視するのは、この多くの軽度者がそのまま重度へとスライドした場合、途端に介護保険が立ち行かなくなってしまうこと。しかしながら、この層で圧倒的に多いのは生活不活発病と言われる廃用症候群。すなわち、改善が見込める人が多くを占めており、重症化予防によって事態を改善できる可能性は十分にあるのである。
和光市がまず行ったのは、どの圏域に、どのようなニーズを持った高齢者が、どのくらいいるのかを正確に把握するための「日常生活圏域ニーズ調査」だ。個別記名式で実施し、未回収のところは全戸訪問。このきめ細かい調査によって、介護のみならず医療、住まい、生活支援、福祉権利擁護などさまざまな課題を抽出した。その解決策として、医療や住まいとの連携も視野にいれた計画策定をマクロな視点で行い、それを実際のケアマネジメントにつなげていく、ということを和光市では10年以上にわたり続けてきた。
大切なのは、わが町の方針を
市民に具体的に示すこと
一方で重要なのが、市民に対して“わが町の方針”をしっかりと明言すること。和光市では、基本計画の中で“在宅重視”“予防重視”という方針を明確に提示し、市民に呼び掛けてきた。「大切なのは、市民に対して安心・安全をどう届けるか。特養並みの医療と介護が住まいにあるということを示せなければ、市民の施設志向、病院志向からの脱却は難しい。同時に、重度者も軽度者も地域で予防ができることをアピールすることも重要」と氏は話す。
一連の取り組みの成果がよく表れているのが、和光市における要介護度の構成比だ。平成26年度のデータでは、要介護認定者全体に占める要支援1~要介護1の割合は38.1%と、全国より大幅に少なくなっているが、これは多くの軽度者から自立へと移行しているためである。また、要介護2や3から要介護1への移行も多く、さらには要介護4と5も減少している。軽度および中度への自立支援型のケアが、重症化を遅らせることができることを、この結果がはっきりと示している。現在、和光市の平均寿命は県内トップクラスだが、一方で要介護認定率は県内でも低い水準を維持している。
次なる展開として和光市で進められているのが、高齢者、子ども、障害者、生活困窮者への各種ケアマネジメントを中央で一元化していくこと。現在、それぞれの問題に対応するセンターが個別に設けられているが、これを平成30年には全てを統合する計画だ。氏は、「ライフステージ全般の相談を受けられる、ゼネラルな仕組みを構築していきたい」と展望を述べた。
在宅サービスの拠点を築き
ワンストップサービスを可能に
地方創生のために、地域の中小病院に何が求められるのか。日本医師会常任理事の鈴木邦彦氏は、自らが理事長を務める志村フロイデグループの取り組みを紹介した。
常陸大宮市は5つの町村が合併してできた自治体で、市の中心部の高齢化率は全国平均程度だが、北部の地域では35%を越えるなど、同じ市内でも実情は大きく異なっている。志村フロイデグループは、その広範なエリアの各所に事業所を設け、保健・医療・福祉の総合的なサービスを展開してきた。
大きな特徴は、地域リハビリテーションの理念に基づいたサービスにある。リハビリテーション科では現在、100名を超えるセラピストが活躍。入院、外来、訪問リハに加え、リハ強化型デイサービスも開設しており、デイケアと同等の効果を出している。
もう一つの特徴は、独自の在宅支援体制を構築していること。在宅サービスの拠点として「志村フロイデ地域包括ケアセンター」を開設しており、訪問看護、訪問リハビリ、訪問介護、訪問入浴、配食までさまざまなサービスが、ここを拠点に連携。在宅での幅広いニーズに対応できる〝ワンストップサービス〟を行っている。
また、昨年4月には、病院の建て替えを機に電子カルテを導入。患者の診療記録や検査結果、薬の処方内容などの情報を介護を含む多職種で共有できる仕組みを構築した。ほかにも、建て替え時の仮病棟を活用して、デイサービスと小規模多機能を展開する「フロイデ総合在宅サポートセンター」、元気な高齢者のための「アクティビティセンター」、さらには子どもも遊べる「リハビリ公園」などを整備。元気な人も病気を持つ人も、あるいは子どもからお年寄りまで、全ての人が集まる地域の拠点を築いている。
全世代・全対象型の
地域包括ケアを推進
続いて 氏が紹介したのは、独自の地域活性化プロジェクトだ。志村フロイデグループの有志が平成22年に立ち上げたボランティア組織「フロイデDAN」では、専門性を生かして地域の活性化、まちづくりに貢献するさまざまな活動を行っている。その一つが、住民が気軽に利用できるコミュニティの拠点として立ち上げた、「コミュニティカフェBAHNHOF」。商店会との連携による買い物支援、サークル活動、ペーパーフラワー教室などさまざまな活動を通じて、地域の人のつながりを創り出している。
そしてもう一つ、力を入れてきたのが少子化対策だ。24時間対応の院内保育所の開設や、短時間勤務制度の導入など、仕事と子育ての両立を可能にする職場環境づくりを推進。現在は同グループの育児休業取得率は100%となっており、医療機関で数少ない「くるみんマーク」(厚労省が認定する子育てサポート企業)にも認定されている。最近では、同グループで毎年20組以上が結婚しており、出生率も高い数字で推移。これが自治体全体の出生率を押し上げている状況だ。
以上を説明した上で氏は、これからは病院も少子化対策や人口減少問題などにしっかりと向き合っていく必要があると強調。「中小病院は地域と運命共同体。単に高齢者対策だけでなく、〝全世代・全対象型地域包括ケア〟の実現に取り組んでいくことが、明るい地域の創造につながる」と結んだ。
スムーズな在宅移行を支える
「アセスメント入所」
つしま医療福祉グループ代表の対馬徳昭氏は、社会福祉法人ノテ福祉会における、「特別養護老人ホームを核としたノテ地域包括ケア」の実践について報告した。
ノテ福祉会は、北海道札幌市を本拠地に特養、老健、グループホーム、小規模多機能など幅広い事業を展開しており、特養を核にしながらこれらの事業をフレキシブルに展開する「ノテ地域包括ケアシステム」を構築している。
どのようなシステムなのか。特徴の一つが、退院後に行われるアセスメント入所だ。在宅に戻る前に、まずは老健「げんきのでる里」に入所し、多職種でアセスメントを実施するもので、その人に合ったケアプランと介護サービス計画を作成の上、在宅に移行する。
目的は、利用者のニーズに合った本当に必要なサービスを在宅でしっかりと提供すること。例えば、ノテ福祉会の特養では要介護度4の利用者に対し、1日平均8回のサービスを行っているが、居宅支援事業所で作成しているケアプランのうち訪問介護では、要介護5で1日1回60分のサービスで終わってしまっている。一方、定期巡回では訪問の効率性が重視されるが、残念ながら利用者がサービスを必要とするタイミングでサービスの提供がされていない。アセスメント入所の最大のメリットは、その利用者がどの時間にどんなサービスが必要かを具体的に把握できること。そして排泄が自立していなければ、その理由がどこにあるのかを分析。トイレに行ってしゃがむのが難しいのか、あるいは立ち上がることができないのか。立ち上がりが問題なら、入所中に立ち上がれる状態までリハビリをして在宅に戻す、といったきめ細かい対応を行っている。
特養のショートステイで
在宅継続をバックアップ
一方、在宅に戻ってからはフレキシブルなサービス提供体制で、利用者の在宅生活を支えている。身体介護中心の高齢者には定期巡回、認知症の高齢者には小規模多機能で対応。小規模多機能で特に力を入れているのが訪問で、多い事業所では1か月に1600回にも達している。この仕組みをバックアップしているのが、特養の存在。家族が手に負えない状況に陥った際、特養のショートステイでケアを行い、安定したら在宅に戻すことによって、在宅継続を支援している。
そして、こういった一連の取り組みを支えているのが、ノテ福祉会が独自に開発した情報共有システムだ。「中重度の高齢者を支えるには、その人が必要とする全ての社会資源がネットワークを構築し、情報を共有する必要がある」と対馬氏。関わるスタッフが利用者の情報をしっかりと把握することで、一日でも長く在宅で過ごせるよう支援している。
さらに氏は、5月20日に地域包括ケア推進研究会より発表された、「提言書」についても言及。その一番の目玉は、定期巡回、小規模多機能、看護小規模多機能の3つのサービスを1つにまとめた新サービス「新型多機能サービス」を提案していることにある。その意図について、「定期巡回はなかなか伸びないが、小規模多機能でたくさん訪問できれば、定期巡回は必ずしも必要なくなってくる。この新サービスは、実態をふまえてより展開しやすい仕組みとして考案されたもの」と説明した。これからの地域包括ケアの一つのカギになる、との見方を示した。
シェアリングシステムで
高齢者の生活を支える
社会福祉法人佛子園の雄谷良成氏が紹介したのは、石川県輪島市における“シェアリングシステム”を活用したまちづくり「輪島KABULET」だ。ネーミングの由来は、「いろいろな人が関わって、何かにかぶれていくようなまちをつくりたい」というもの。漆のまちとして栄え、バブル時代には180億円もあった売り上げが30億円を切り、産業人口の多くが周辺都市に流出。能登の中でも圧倒的な高齢化社会を迎えている。
その輪島市で進められているシェアリングシステムとは、大きく消費を進めていく時代から、分け合う時代への転換を図るもの。例えば、米の袋を持てない独居の高齢者がいたら、その時間帯に手が空いている人がそこへ駆けつけてサポートするなど、空いている時間や労力をシェアすることで、助け合う仕組みを構築している。あるいは、自動車や電動カートをシェアする仕組みも展開。高齢者はもちろん、移住者、観光客もシステムを使えるようにすることで、人の関わり合いを創出し、交流人口を増やしている。

「2018年医療介護の制度・報酬改革のあるべき姿を探る」
~2025年改革のシナリオのターニングポイント2018年同時改定のインパクトとは~
我が国を代表する政策立案者、研究者、業界団体代表の皆様に一同に集まっていただきシンポジウムを開催。危機的な財政下の制度の持続可能性と地域包括ケアシステム構築をはじめとした、国民への最良の医療介護サービス提供のためのあるべき改革にてついて討論いただいた。
国民皆保険と地域包括ケアシステム
2大目標を掲げる2018年改定
消費増税をめぐる議論は、経済成長か財政再建かという旧来型の二元論に終始したが、第一級の経済学者の間でも諸説紛々だった。結局は骨太の方針で示された「経済成長なくして財政再建なし」に従うかのような趣旨で決着したが、改めて着目したいのは日本医師会の主張だ。
「経済発展が社会保障の財政基盤を支え、他方で社会保障の発展が生産誘発効果や雇用誘発効果などを通じて日本経済を底支えする」「医療の拡充による国民の健康水準の向上が経済成長と社会の安定に寄与」「老後が不安であるという思いを持つ多くの国民に、安心を示すことは、経済成長を取り戻すための出発点」。目新しい内容ではないが、バランスの取れた視点である。
政府・与党の経済財政政策がどう進むかはともかく、医療介護が直面する課題は、2025年から2040年までをいかにして乗り切るかである。厚生労働省は国民皆保険の堅持と地域包括ケアシステムの構築という2大目標を掲げているが、2018年の診療報酬・介護報酬同時改定で、2040年までのレールが敷かれていく。国民皆保険だけでなく、市町村主義・要介護認定・ケアマネジメントという世界に例のない本格的な介護保険制度も、また堅持の対象である。
この2大目標に向かうには、地方の過疎化と都市部の高齢化が急速に進み、医療介護職の不足が常態化する中で効率的な提供体制を築かなければならない。例えば日本の医療提供体制を支える民間中小病院と診療所は高水準の質を保ち続け、その質をもって在宅支援やワンストップサービスへの展開が期待されている。
18年改定が厳しい内容になりそうなことは必至だが、2021年以降に五輪後不況が襲来すれば、以降の診療報酬改定と介護報酬改定は、さらに厳しくなるのではないか。M&Aによる経営統合や、地域医療連携推進法人による業務統合を進めて、提供体制を効率化する動きが加速するだろう。人口減の地域で事業が成り立たなくなれば、事業者は都市部に軸足を移し、事業者間の優勝劣敗はさらに激しくなっていく。
さる6月5日、都内で開かれたシンポジウムで元公的病院の幹部は「いまだに多くの医療者は様々な課題を厚労省に何とかしてもらおうと考えているが、厚労省から精神的に自立しなければいけない」と親方日の丸意識を戒めた。診療報酬を巡る“梯子外し”という厚労省批判も、あるいは自立意識の不足に由来するのかもしれない。制度・政策の先を行く視野が大切だ。
かかりつけ医が中心の地域包括ケア 郡市区医師会が大きな役割を担う
日本医師会会長
横倉義武氏
日本医師会が目指す「かかりつけ医を中心とした地域包括ケア」。今年4月、「日医かかりつけ医機能研修制度」をスタートさせた。日医は今後の医療提供体制にも独自の見解を示している。横倉氏に要旨を聞いた。
■日本医師会では地域包括ケアシステムの推進で郡市区医師会に大きな役割を期待していますね。
横倉 わが国では、現在、地方の過疎化の進展、都市部の急速な高齢化が大きな課題になっており、健康寿命を延伸させることが重要なテーマとなっています。
このような中で、国は地域包括ケアシステムの構築を進めていますが、日医では、その中心的な役割を各地の郡市区医師会が担うべきであると考えており、その積極的な関与を求めています。郡市区医師会は現在でも市区町村行政との連携、ケアマネジャー等多職種との連携などでも大きな役割を果たしていますが、これからは、まちづくりにおいても中心的な役割を果たすことを期待しています。
■その主体として位置づけているのが、かかりつけ医だと思います。かかりつけ医にはどのような機能を持って欲しいと考えていますか。
横倉 日本医師会が目指しているのは「かかりつけ医を中心とした地域包括ケア」で、かかりつけ医を中心として切れ目のない医療介護を提供していく方針です。かかりつけ医については、社会保障制度改革国民会議報告書にも「大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診は『かかりつけ医』に相談することを基本とするシステムの普及、定着は必須」と盛り込まれました。日医と四病院団体協議会は、かかりつけ医をこう定義しています。
「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」。この定義に基づいて
日本医師会は、かかりつけ医の機能について①患者中心の医療の実践②継続性を重視した医療の実践③チーム医療、多職種連携の実践④社会的な保健・医療・介護・福祉活動の実践⑤地域の特性に応じた医療の実践⑥在宅医療の実践。以上の6点を定めています。
■今年4月から開始した「日医かかりつけ医機能研修制度」についてご説明ください。
横倉 この研修制度の実施主体は研修を希望する都道府県医師会で、研修プログラムは基本研修、応用研修、実地研修で組まれています。基本研修では日医生涯教育認定証を取得し、応用研修では日医が行なう中央研修や都道府県医師会・郡市区医師会が主催する研修を受講します。さらに実地研修では保健・医療・介護・福祉活動、在宅医療、地域連携活動などを実践します。この3つの研修を3年間で修了すれば、都道府県医師会が修了証書または認定証を発行します。
このことが、当該医師が地域のかかりつけ医として活動し、研鑽を続けていることを示すものとなり、地域住民からの一層の信頼につながることを期待しています。
■都道府県医師会の実施状況はいかがですか。
横倉 研修制度を今年4月から実施している都道府県医師会は21カ所、実施を決定した医師会は8カ所、実施検討中は18カ所で、実施を予定していない医師会は皆無となっています。
■地域医療構想が病床削減に誘導されそうな動きについて、日医は異論を提示していますね。
横倉 病床の機能分化、連携強化という方向性自体は間違っていません。ただし、国や都道府県が目標値を定めて一律に推し進めることは適切ではありません。人口の集中や散在、あるいは在宅医療の基盤づくりの進み具合など、それぞれの地域の実情を反映させることが必要です。例えば、ある地域では慢性期機能の必要病床数を多く算定し、また他の地域では在宅患者数を多くするようにすべきです。
「地域医療構想は病床削減のツール」と言われることがありますが、行政が病床を削減するツールに活用するとしたら、それは間違いです。
地域医療構想の策定では データに基づいた議論が不可欠
産業医科大学 公衆衛生学教室
教授 松田晋哉氏
慢性期医療の適正化を精査すると、療養病床の削減が介護給付費の増大を招くことが見えてきた。地域医療構想の策定と地域包括ケアのポイントについて松田氏に聞いた。
■地域医療構想の策定は地域の医療現状把握と将来の疾病構造の予測から始めますが、福岡県の現状はどうなっていますか。
松田 平成25年度厚生労働科学特別研究事業で、NDBデータによって福岡県における入院医療の自己完結率を分析しました。福岡県の京筑医療圏では、救急の自己完結率は85%で、搬送時間も新生児の救急で長い傾向がありますが、他の年齢層に対する搬送時間は許容範囲であると言えます。救急の受け入れ能力にはとくに問題はないので、必要な施策は小児入院体制の確保です。県内4大学の小児科教室と協議の上、2つのDPC病院のいずれかで対応することが求められています。
■慢性期医療の分析結果はいかがでしたか。
松田 慢性期医療の適正化では、療養病床の一部を回復期に転換した上で、さらに推計結果に基づいて163床を減少させる場合、その代替となる在宅医療と介護サービスの確保が必要となります。しかし介護サービスへの移行は介護保険給付の増大につながるため、その影響を事前に検討する必要があります。
一方、療養病床を一定程度維持する場合は、平成29年度における療養病床の看護基準の経過措置廃止に伴う20対1の義務化に対応するために、看護師と看護補助職の確保が必要になってきます。
■こうした現状に対して、医療現場ではどのような問題意識が見られますか。
松田 福岡県医師会が今年3月に発表した「療養病床及び地域包括ケア病床に関する調査報告書」には、次のような見解が記載されました。
「政策的に病床削減を誘導しなくても、福岡県内の多くの地域で『看護師不足』、『投資の困難性』のために病床減少が進み、その結果として在宅でケアを受ける高齢者が増加すると予想」「療養病床の入院患者の平均年齢が80歳を超えているということは、受け入れ家族も高齢化している可能性が高く、したがって退院可能の条件である『家族の受け入れ』は期待しにくい」「介護サービスの充実に関しては、地区医師会長の多くがその確保は難しいと予想」。
こうした見解も踏まえると、
急性期以降、とくに慢性期の高齢者をどのように地域でケアするかが、これから各地域の医療のあり方を決め、地域包括ケアの確立が求められてきます。
■地域包括ケアの推進に伴って医療介護施設の役割も変わってくると思います。
松田 平成19年の調査ですが、「地域コミュニティ政策に関する自治体アンケート調査」によれば、コミュニティにとって福祉・医療関連施設は狭義の医療・介護だけではなく、安心のための重要な拠点と考えられています。医療介護施設が提供している「安心を保証する機能」を地域に開放し、展開していくという発想が必要ではないでしょうか。「医療介護施設門前町」「フォーマル部門によるインフォーマルサービスの提供」という発想です。
■地域包括ケア推進のポイントは何でしょうか。
松田 在宅ケアの基本は「住」です。サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能施設、シェアハウスなど地域の実情に合わせた多様な住まいの提供体制によって、高齢者を孤立させない政策が大切です。食の確保、買いもの支援、移動手段の確保など生活を支える仕組みも必要です。
さらに安心できる市街地の賑わいづくりが地域包括ケアのポイントになってきます。福岡県の飯塚市医師会館「サンメディラック飯塚」は、1階が西鉄のバスターミナル、その上階に医師会の急患センター、検診検査センター、訪問看護ステーションが入り、分譲マンションも62戸が組み込まれています。安心で便利なため、高齢者が郊外の自宅を売って移住しています。
医療計画と介護保険事業計画 2つの連結が地域包括ケアの鍵
厚生労働省 保険局長
唐澤 剛 氏
地域包括ケアをどのように理解すべきか。構築のポイントは何か。「超少子高齢社会を乗り切る方法は地域包括ケア以外にない!」と断言する唐澤氏に聞いた。
■これだけ地域包括ケアシステムがキーワードとして使用されているにもかかわらず、相変わらず分かりにくいという意見が多いのも事実です。
唐澤 医療介護総合確保推進法で地域包括ケアシステムについて定義されていますが、いろいろな要素が入っていて分かり
にくいかもしれません。地域ケアなら分かりやすいのですが、包括が入ると分かりにくくなってしまいます。何を包括するのか?それは医療と介護の包括であり、生活
支援とまちづくりの包括です。 私は地域包括ケアを縦軸と横軸で説明していま
す( 別掲の図参照)。この図が示すように、地域包括ケアの構築には、急性期を川上として
川下を見るプロフェッショナルの視点ではなく、住まいを拠点として社会全体を眺める生活
者の視点が不可欠です。
■医療と介護を連携させるポイントは何でしょうか?
唐澤 二次医療圏で作る医療計画や医療ビジョンと市区町村で作る介護保険事業計画を、どのようにつなげるかが非常に重要です。縦軸をつなげることは簡単そうに見えるかもしれませんが、簡単ではありません。同じ患者さんに対して急性期医療の原理は救命と治癒ですが、回復期と慢性期と介護は『今年の孫の誕生日にお祝いをしたい』など、その人らしい暮らしを送らせてあげることです。
急性期病院のドクターとナースは、退院した患者がど
んな暮らしをしているのか、デイサービスに通ったり訪問看護を受けたりしているのかなどを
見て理解すること、慢性期や介護のスタッフと話をすることが重要です。
■地域という言葉をどのように理解したらよいでしょうか。中学校区という区域だけでなく、もっと本質的な理解が必要だと思います。
唐澤 地域包括ケアが対象とするのは、制度上は中学校区ですが、特定の場所ではなく、人のつながりがあり、顔の見える関係が形成されていることが大切です。ひとり一人に寄り添
い、その人らしい物語を尊重することです。
例えば滋賀県東近江市で運営されている三方よし研究会では「地域まるごとけあ」と称
して、顔の見える関係が形成されています。100人以上の医療介護関係者などが毎月1
回のケア会議に出席し、皆が参加できる円形テーブルで議論が交わされ、定期的な研修会や市民との交流イベントも実施されています。こうした取り組みには医師会の協力も大切
ですが、医師には、威張らない懐の深いリーダーシップを発揮していただきたい。
(文/編集部)
地域包括ケアはどう在るべきか?行政、医療、介護それぞれの見解
地域包括ケアシステムは全国一律の政策パッケージではなく、地域の実情に合わせた「ご当地システム」だが、行政、医療、介護それぞれの立場でも捉え方が異なっている。厚生労働省、医療関連団体、介護関連団体が、地域包括ケアの在るべき姿と関わり方を報告する。
【座長】
日本医師会 常任理事 鈴木 邦彦 氏
【シンポジスト】
厚生労働省 老健局 老人保健課長 佐原 康之 氏
日本医療法人協会 会長 加納 繁照 氏
日本慢性期医療協会 会長 武久 洋三 氏
全国老人保健施設協会 会長 東 憲太郎 氏
地域包括ケアシステムの推進と
介護保険制度の持続可能性の確保
厚生労働省老健局老人保健課長の佐原康之氏は、平成26年介護報酬制度改正について「主な内容は地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化である」と振り返った。
地域包括ケアシステム構築のポイントはサービスの充実と重点化・効率化である。サービスの充実では「高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするために」(佐原氏)地域支援事業を充実させ、在宅医療・介護連携の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実・強化に着手した。もうひとつのポイントである重点化・効率化では、全国一律の予防給付を市町村の地域支援事業に移行し、さらに特養の入居者を原則として要介護3以上とした。費用負担の公平化では「低所得者の保険料軽減を拡充し、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直した」(佐原氏)。
佐原氏は社会保険審議会介護保険部会の主な検討事項案も取り上げた。「介護保険制度の見直しに当たっては、これまでの制度改正などの取り組みをさらに進めて、地域包括ケアシステムの推進と介護保険制度の持続可能性の確保に取り組むことが重要と考えられている」という前提のもとで、次のような検討項目を挙げた。
地域包括ケアシステムの推進では、4つの項目が候補に挙がっている。第一に保険者機能の強化など地域の実情に応じたサービスの推進。第二に医療と介護の連携で、慢性期の医療・介護ニーズに対応したサービスのあり方。第三の項目は地域支援事業・介護予防の推進。そして第四にサービス内容の見直しや人材の確保である。
一方、介護保険制度の持続可能性の確保では、給付のあり方と負担のあり方を検討する。
これらの取り組みは2025年に照準を合わせたものだが、2025年以降も65歳以上人口は増え続け、15歳未満人口は減少し続ける。佐原氏は「2025年は入口に過ぎない」と警鐘を鳴らした。
人口密度の高い地域では
民間病院が公的病院より優位
日本医療法人協会会長の加納繁照氏(社会医療法人協和会・社会福祉法人大協会理事長)は「日本の医療は民間病院が支えている。急性期も慢性期も精神科も民間病院が支えている」と明言し、その根拠を示した。民間病院は国内の全病院数の8割、病床数の7割、救急搬送数の6割を占めている。これに対して公的病院の比率はそれぞれ2割、3割、4割になることから加納氏は「2・3・4/8・7・6の法則」と述べた。
総務省消防庁の調査によると、平成26年度の救急搬送数における民間医療機関が占める割合が70%を超えたのは6都府県、60%を超えたのは11県、50%を超えたのは21道県だった。一方で公的医療機関が占める割合は70%超が14県、60%超が21県、50%超が26県だった。総人口に対する比率では民間病院が優位の地域は総人口の65・4%、公的病院が優位の地域は34・6%だった。
この結果について加納氏はこう分析している。
「日本の総人口の3分の1を占める人口密度の低い26の地域では公的病院が優位にある。この地域の民間病院は公的病院と補完的な関係を築いて運営していく必要があるのではないだろうか。救急搬送の50%以上を民間医療機関が受けている都道府県では、2025年に向けて65歳以上人口がさらに増加し、高齢者救急受け入れの需要が拡大する。民間医療機関が受け入れないと高齢者救急は崩壊してしまうだろう」。
医療介護職の人手不足解消には
他産業の中高年の参入が不可欠
日本慢性期医療協会会長の武久洋三氏(医療法人平成博愛会理事長)は「地域包括ケアシステムとは何か?」と問いかけた。
「医療の後に介護があり、介護の後に医療が必要なように、医療の支えのない介護はない。地域包括ケアシステムも医療の支えがあって初めて成立する。各パーツが絶対に断らないことで地域包括ケアシステムが成立する。バッグベッドの中核病院は24時間365日、在宅の軽中度の急性増悪患者を受け入れる意志のあるところに限られる。モンスターや認知症、超高齢・超重症など診たくない患者を断る利己主義・自己中心主義の病院は退場すべきだ」。
退院支援については車椅子自立を提言した。「たとえ動けなくても、まずは口から食べて自分で排泄できることは人間の原点」という見解に立って「超高齢者は、自ら食べて、自ら排泄できるようになれば、車椅子自立を確立すべきだろう。そうすれば寝たきりにならずに自宅に戻れる人が増えるだろう」。
今後最も対処が問われてくる疾病は認知症だが、この課題に慢性期病床はどう対処すべきなのだろうか。高齢の認知症患者が複数の疾病を伴っていることや、精神科病床が削減されていく流れを踏まえて、武久氏が提言するのは、精神病床の内科や慢性期病床への転換だ。
「認知症の本人も家族も精神科病院に入院したくない。内科病床に入院して総合診療医と精神科医の共診で診るべきだろう」。
武久氏は看護職と介護職の人手不足対策にも言及した。平成28年の看護師国家試験の合格者は約5万5000人、准看護師は約1万7000人、介護福祉士は約8万8000人。「これ以外に介護職の新人は約10万人いる」(武久氏)。つまり約26万人の看護・介護職が誕生したことになる。一方、昨年の出生数は約100万人で、その多くが社会人になる2035年に、26万人にコメディカルを加えた約30万人が医療介護職につくことは考えられない。同一年齢の就労者の3分の1が医療介護職に就くことは、産業構造からしてあり得ない。
「元気中高年に医療介護職に参入してもらわないと、どうにもならない。シャープや東芝のような大量の人員整理はこれからも起こり得るし、再就職の問題に直面する。医療介護職を受け皿とするために、働きながら学べる夜間准看学校をどんどん増設すべきだ。ひょっとしたら東大出身の准看学生が誕生するかもしれない」(武久氏)。
医療の質を担保するため
所定疾患施設療養費の拡大を
全国老人保健施設協会会長の東憲太郎氏(医療法人緑の風理事長)は、地域包括ケアシステムの構築には、本人と家族が自宅で暮らす覚悟が必要だと強調した。
「独居、老老介護、中重度者、認知症高齢者であっても、できる限り自宅で生活する覚悟を持てるように医師は説明すべきだ。BPSDや中重度者であることを理由に、安易に終生施設を紹介してはならない。覚悟を支える様々な介護サービスを説明して、不安を取り除くのだ」。
地域包括ケアにおいて老健が担う役割については、リハビリテーションの充実、R4システムを基盤としたケアの充実、医療の充実、認知症へのより高度な対応の4点を挙げた。このうち医療の充実については、医療の質を担保するために所定疾患施設療養費の拡大が必要で、現在の3疾患(肺炎、尿路感染、帯状疱疹)から6~9疾患への増加を要望する方針だ。
介護職員の処遇改善については、キャリアアップへの財源確保を求めた。
「月1万2000円の介護職員処遇改善加算や、一億総活躍プランで月1万円を賃上げしても抜本的な改善にはならない。介護職に人気がないのは、この仕事に就いて成長できるというプランを描けないからだ。介護報酬とは別に基金を設けて、キャリアアップ段位制度や認定介護福祉士制度など専門技術の向上を目指す取り組みを推進する必要がある」。
一施設当たりの請求額は
年間650万円のマイナス
全国老人福祉施設協議会副会長の瀬戸雅嗣氏(社会福祉法人栄和会理事・事務局長)は「社会福祉法人の内部留保が話題になった時に、社福全体の経常利益率が8%もあると報道されたが、現実はそうではない」と反論をして、社福の経営悪化を取り上げた。
全国老施協の調査によると、改定率がマイナス2・27%となった平成27年介護報酬改定を受け、一施設当たりの月額請求額は約54万円の減少し、年間では約650万円のマイナスとなった。また年額平均で1411万円増となる事業所がある一方で、2560万円減の事業所もある。赤字施設は27・9%と過去最大となった。瀬戸氏は「加算取得要件に対する規模的・地域的条件などから、法人・施設間の格差がますます拡大している。人材確保難から賃金アップが収支に影響している」と指摘した。
全国老施協が重点的に取り組んでいるのは認知症ケア、看取り介護、生活機能向上のための機能訓練、地域包括ケアである。例えば看取りケアでは、全国老施協が調査した2121施設のうち74%が看取りの実績を持ち、45・7%が看取り加算を取得した(平成24年度実績)。「看取りは看取り期の対応ではなく、元気なうちから最期までその人らしく生き切ってもらうことだ」という。
地域包括ケアについては「住んでいる場所が地域であればいいとか、ケアシステムができていれば実現するというものではない」という認識を示した上で次のような見解を述べた。
「地域に住んでいる人に専門性のあるケアを届けることが必要で、その拠点に特養や軽費老人ホーム・ケアハウスがある。また、軽費老人ホーム・ケアハウスは低所得者や生活困窮者のセーフティーネットの役割も果たす。施設に住んでいても地域とのつながりを持って生活してもらうことが大切で、これが尊厳のある暮らしにつながっていく」いわば居宅や地域での生活が維持されることに、地域包括ケアの真価を求めている。(文/編集部)

27年9月に成立した医療法改正法案。改正により地域医療連携推進法人が29年度を目処に施行する予定となっています。地域医療連携推進法人には、公立病院、医療法人の他、社会福祉法人なども参画できるとされており、病院・介護施設の再編統合が進むものと予想されています。法律改正に至った経緯から、実際の地域医療連携推進法人の設立から運用について、それぞれの演者のお立場からお話いただきました。
地域医療連携推進法人は、
来年4月の施行に向け、
各地で設立の動きが広がっている。
様々な連携のパターンがある。
厚生労働省医政局 医療経営支援課
課長補佐 水野忠幸氏
公的病院と民間病院、民間病院同士など地域医療連携推進法人の設立が検討されているが、設立に際して最も問われるのは「何を目的に設立するのか?」である。法人設立の考え方を水野氏が解説する。
■地域医療連携推進法人制度の趣旨は何ですか。
医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として地域医療連携推進法人の認定制度を創設した。これにより競争よりも協調を進め地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保。
■設立が検討されている事例を教えてください。
大学病院、市立病院、独立行政法人立病院が機能分担や業務連携を目的に参加するケース。中規模の医療法人同士で診療科目の分担、職員の相互交流などで連携するケース。あるいは、がん治療を専門とする医療法人同士で薬剤の共同購入や高額医療機器を使った治療で連携するケースなどが検討されています。
■地域医療連携推進法人の設立で焦点になるのは何でしょうか。
順序としては初めに中心メンバーを集めることですが、その前提は「新法人を設立して何をやるか」。これが大事です。新法人を設立しただけで何かハッピーなことがあるわけではありません。何をやるか、そのツールが新法人なのです。
■地域医療連携推進法人制度の発足に際して、当面、どのぐらいの法人が設立される見通しですか。
厚労省には約30件の相談がきていますが、法人制度施行日の平成29年4月2日から30法人がスタートするとかどうかは分かりません。
■社員は各一個の議決権を有するとなっていますが、収益1億円の法人と収益100億円の法人の議決権を同じ一個と規定することは不合理ではないでしょうか。
法人ごとに社員となっており、議決権は社員一票が原則であり、その例外として、法人の規模を問わず、不当に差別的な取り扱いをしないことと規定されているのであり、不合理なことではありません。事業規模が大きいから必ず議決権が多くなるということではありません。
■一つの医療法人が複数の病院を経営している場合、地域医療連携推進法人に全ての病院を加盟させなければならないのですか。
地域医療連携推進法人は原則として二次医療圏で運営されるので、加盟対象になるのは同一圏内の病院であり、同じ法人の経営でも圏外の病院は対象になりません。
■連携法人設立の許認可は都道府県知事の専管事項になっているが、他県の法人と連携法人を設立したほうが合理的な場合、許認可権はどうなるのでしょうか。
県をまたがって法人を設立する場合は複数の知事が関係してきますが、どの知事が担当するかは行政当局同士で調整します。「ここは!」と思う都道府県に申請を出していただきたいと思います。
■改正医療法を受けた医療法人制度の見直しのポイントは何でしょうか。
医療法人の経営の透明性の確保とガバナンスの強化が挙げられます。負債50億円以上または収益70億円以上の医療法人、または負債20億円以上または収益10億円以上の社会医療法人は、医療法人会計基準に従って貸借対照表と損益計算書を作成し、公認会計士による監査・公告が義務付けられます。これは平成29年4月以降の会計年度において試行・適用されます。
医療法人は法人役員と特殊な関係のある事業者、例えば近親者やそれらが支配するMS法人との取引の状況について都道府県知事への報告が義務付けられます。報告が義務付けられる取引の範囲は、当該事業収益または事業費用が1000万円以上であり、かつ総事業収益または総事業費の10%以上を占める取引などです。
さらに新制度では、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任が規定され、理事会の設置、社員総会の決議による役員の選任などに関する所要の規定も整備されました。
※貴重なご講演の中から一部を質問形式でまとめました。 「Visionと戦略」編集部
医療法人に対する外部監査は
金融庁を意識して厳格に実施される
東日本税理士法人所長
公認会計士 長 英一郎氏
監査法人の監査品質が問われている中で、医療法人に義務付けられる外部監査は相当厳しく実施されるという。外部監査による健全経営の推進というプラス面もあるが、一方で何が懸念されるのか。長氏に聞いた。
■医療法人制度の見直しによって外部監査が義務付けられます。経営の透明性を確保することは時代の要請ですが、医療法人の経営にどのような影響を及ぼしそうですか。
外部監査の実施には健全経営の推進というプラス面がありますが、実は法人経営にとってはデメリットもあります。主に3つです。
第一にコストです。任意監査ではなく法定監査なので監査法人は厳しい監査を実施しますが、厳しさの基準は金融庁のチェックに耐えられるかどうか。金融庁を意識した監査を実施するので、厳しく臨まざるをえず、それは監査報酬などのコストに跳ね返ってしまいます。
第二に意思決定の遅延です。内部統制の強化が求められ、会議や稟議書など意思決定の手続きの仕組みを構築しなければならなくなるため、これまでのように理事長による即断即決ができなくなります。
第三のデメリットは銀行との関係です。新制度には「退職給付引当金には、退職給付に係る見積債務額から年金資産額を控除したものを計上する」と規定されています。信用力の高い法人なら問題はありませんが、退職給付引当金を3~5億円計上することで赤字を出した法人に対して、銀行は運転資金や設備投資などの融資を見送るというリスクを想定されます。仮に、債務超過に陥った法人への融資の回収を次年度に見込めなければ、融資額の一括返済や新規融資ストップという措置が下されることになります。
■退職給付引当金の計上について工夫できる要素はありますか。
退職給付引当金は最大15年で償却できる制度ですが、監査初年度に一括償却をして赤字を出してしまい、次年度以降の決算を楽にするという方法もあります。
■医療法人の役員の近親者が支配する法人との取引についても、情報開示が要求されますね。
関連法人との取引は都道府県の調査対象になります。取引内容は「関係事業者との取引状況に関する報告様式」に記載しますが、取引金額の根拠も記載しなければなりません。取引金額が世間相場から乖離していれば是正を求められます。
■監査対象となる医療法人は貸借対照表と損益計算書の公告も義務付けられます。懸念されることはありますか。
注記事項の開示も義務付けられることです。関連会社との取引状況だけでなく、後発事象として患者さんからの損害賠償請求などナーバスな情報も記載しなければなりません。
■監査法人は法定監査に備えて、どんな体制を整備しつつあるのでしょう?
医療法人だけでなく改正社会福祉法を受けて社会福祉法人の法定監査も義務付けられるので、監査法人への引き合いが増えています。私どもの事務所が公認会計士の募集をかけても応募がなかなか来ないほど公認会計士が不足している状況で、法定監査が始まれば“監査難民”となる医療法人も出てくるかもしれません。
■地域医療連携推進法人に向けた流れにあって、注目している事例はありますか。
九州地方の民間A病院は平成22年から公立B病院に事務員を2名派遣して一体的な経営を目指してきましたが、A病院を退職してB病院に就職するという手続きを取っていました。この状況に対して両院は地域医療連携推進法人を設立して、柔軟な人事交流、資金の融通、共同購入などを図っていこうと計画しています。
※貴重なご講演の中から一部を質問形式でまとめました。 「Visionと戦略」編集部
【平成28年5月17日開催】
マーケティング、リソース、経験
3つの強みで回復期リハ病院を毎年新設
カマチグループ
一般社団法人巨樹の会
副理事長 桑木晋氏
カマチグループの急性期病院6施設の救急搬入件数は年間2万2000件、回復期リハビリ病院では14施設の総病床数が2366床に達する。回復期リハビリ病院を毎年1施設以上新設する同グループ巨樹の会の戦略を聞いた。
■埼玉厚生連から買収した新久喜総合病院(300床)の経営状況はどのように変化していますか。
新久喜総合病院としての開院は今年4月1日で、300名強のスタッフ数だった同院に巨樹の会から医師6名、看護師120名、さらにPTとOTを含め150名を派遣して、救急の受け入れを急増させました。
その結果、4月実績では、病床稼働率が月初の45・0%から月末には64・9%に改善されました。昨年4月との対比では1日平均の新規入院患者数が13・3人から17・9人に増え、平均在院日数が13・4日から11・6日に短縮されました。5月か6月には単月黒字に転換すると見込んでいます。
■巨樹の会は平成21年以降、首都圏で毎年1ヶ所以上に回復期リハビリテーション病院を新設しています。
なぜ毎年新しく病院を開設するのでしょうか?その理由は大和民族のための医療を展開するためです。回復期リハビリは患者満足度の高いサービスであり、多くの方々に体験していただきたいという思いに加え、人口当たりの回復期ベッド数のばらつきを是正して、リハビリ難民をなくすという方針があります。
そして、なぜ毎年新規に病院を開設することが可能なのでしょうか?それは病院の新規開設が可能かどうかを検討するマーケティング能力、新規立ち上げを可能とする十分なリソース、新規立ち上げの経験の3つを保有していることが挙げられます。
■マーケティングのポイントは何でしょうか。
ポイントは3つです。第一に二次医療圏の人口がどの程度で、今後人口が増える地域なのか。第二に交通の便がどうなっているのか。駅からの移動時間、主要道路からの距離などマクロとマイクロの視点で評価しますが、これはスタッフ集めと患者さん集めに影響します。第三のポイントは二次医療圏の人口10万人当たりの回復期のベッド数はどうなっているのか、巨樹の会クオリティに近い競合病院が存在するのか、特定の医療機関による囲い込みなどはないのか、つまり競合の状況を分析します。
マーケットに十分なニーズがあれば、巨樹の会クオリティのサービスを提供すれば必ず事業が成り立つと考えてプロジェクトをスタートさせています。
■リソースの確保にはどのように取り組んでいるのですか。
回復期リハビリテーション病院には医師、看護師、ケアワーカー、セラピスト3職種、MSW、薬剤師、管理栄養士の9職種が関与しますが、なかでも医師、看護師、セラピストの確保が重要です。
新規開設病院では院長、看護師長、看護主任、セラピストの病棟主任などはグループ内異動で対応しています。新規採用については医師は医師個人のツテ、看護師はホームページ経由による中途採用、セラピストはグループ内の養成校の卒業生採用を中心に実施しています。
もうひとつのリソースである資金調達の手段については、銀行借り入れで対応し、変動金利で短期の借り入れがメインです。
■厚生労働省は地域包括ケアシステムの海外展開を構想してしますが、巨樹の会はその流れにコミットすることを考えていますか。
基本的に病院の輸出は無理だと思います。病院勤務者はさほど給料が高くありませんが、人の役に立たなければなりません。この思いを共有するには、やはり同じような文化で、同じような育ち方をした人のほうが望ましく、違う文化の人に指導することはかなり大変です。それに海外に展開する以前に、日本でやるべきことがたくさんあると考えています。
※貴重なご講演の中から一部を質問形式でまとめました。 「Visionと戦略」編集部
【平成28年5月17日開催】
社福の余剰現預金の蓄積メカニズムを解明!
高収益でも支給される“補助金天国”
キヤノングローバル戦略研究所
研究主幹 松山幸弘氏
地域医療連携推進法人制度の端緒となった非営利ホールディングカンパニーを国に提唱した松山氏。新型法人に期待される成果、社会福祉法人の内部留保問題など医療福祉経営の論点を聞いた。
■地域医療連携推進法人にはどのような成果を期待できますか。
スタート時に期待される成果としては、経営管理部門では共同購買によるコスト引き下げ、医療専門人材の共同採用と研修などがあり、臨床部門では患者情報共有とデータベース構築、臨床研究機能の向上があります。これで成果を上げたグループでは、地域における使命感と価値観を共有する信頼関係が醸成され、新規投資を合弁で行なう機会が増えるでしょう。
■地域医療連携推進法人として名乗りを上げている岡山大学メディカルセンター構想は、日本のピッツバーグを目指していますね。
ピッツバーグを目指す条件は「主役が非急性期の事業体」「異文化の多様な人材が切磋琢磨する組織文化」「判断基準が大学の利益でなく地域全体の利益」「医局機能を大学医学部でなくIHNが発揮」など6つです。言い換えれば、県民の医療介護福祉ニーズに近いケアサービス構成の事業体を築き、世界標準のマネジメントができるか、ということが問われます。
■社会福祉法人の内部留保問題についてお尋ねします。松山先生は日本経済新聞への寄稿で内部留保が潤沢である実態を論証しました。反響はいかがでしたか。
日経の「経済教室」に掲載(3月28日)されてすぐに霞が関の複数の組織から詳細説明の要請がありました。
社福約2万のうち内部留保が問題視されている施設経営社福は、厚労省所轄と自治体所轄を合わせて約1万8千です。このうち全国社会福祉法人経営者協議会のサイトに出ていた法人名を頼りに5,531法人の財務諸表を入手、主たる施設種類別、都道府県別に集計分析、その結果をベースに1万8千法人の全体像を推計しました。これにより、借入金を差し引いた余剰現預金が社福全体で2兆円以上あることが確認できました。
■この集計作業を通じて何が判明しましたか。
注目点は、福祉ニーズに積極的に応えるため借金をして事業拡大している社福と新規投資をせず現預金の積み上げに熱心な社福に二極化している社福の構造です。また、所轄庁に提出している財務諸表ではなく簡易版しか開示していない社福、パソコン画面上で読むことができない画像で開示したことにしている社福など、今回の社会福祉法改正の趣旨に反する社福も多く見受けられました。障害者施設中心の社福の平均経常黒字率が7%、3分の1が経常黒字率10%超というのも驚きです。
■問題視すべき補助金受給の例を教えてください。
毎年経常黒字率が10%を超え、現預金が総資産に占める割合が70%という社福に、運営費補助金が毎年3億円以上支給されています。この社福は規模も大きく経営能力が高いわけだから、積極的に新規投資をすべきです。
■ニッポン一億総活躍プランに、保育士と介護職員の給与引き上げが政策目標に示されました。公費に頼らず内部留保を投入できる社福も多いのではないでしょうか。
介護士と保育士の給与引き上げのための公費追加投入は必要ですが、その財源は社福に眠っています。例えば、政府は保育士給与を2%引き上げる方針ですが、保育所専業社福の平均経常黒字率は4.9%です。一方、その収入に占める人件費の割合は約75%です。つまり、保育士給与2%引き上げ財源を追加補助金なしで社福自身に負担させても、 経常利益率が1.5%下がり3.4%になるだけです。
※貴重なご講演の中から一部を質問形式でまとめました。 「Visionと戦略」編集部
【平成28年5月17日開催】